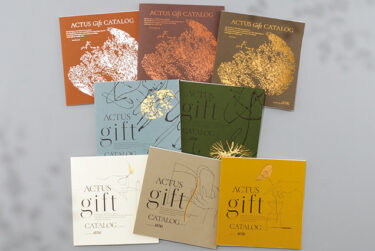原材料のガラスが、まるで宝石のような輝きを放つ美しい切子へ。職人たちの匠の技で削られ、磨かれることで生まれる、大阪の伝統工芸「天満切子」(※1)。創業は大阪でガラス産業が隆盛を誇っていた昭和8年(92年前)。「大阪ガラス発祥の地」の碑は今も大阪天満宮前に残っている。
当初一般的なガラス製品も扱っていた「宇良硝子加工所」が、特殊な技法で生み出したブランドが「天満切子」だ。現在、大阪が誇る伝統工芸として、海外から訪れる国賓への贈答品としても使われている。今回取締役の津田晃宏さんに天満切子のブランディング、商品開発のこだわりなど、お話しを伺った。
江戸時代に伝わった切子
全国には江戸切子や薩摩切子など、それぞれ製法が異なる切子が存在するが、江戸時代、長崎の商人、播磨屋久兵衛が大阪にガラス製法を持ち込んだのが切子の最初とされる。一般的なV字の直線的な製法とは異なり、天満切子は「U字の蒲鉾彫り」と呼ばれる独特の技法が特徴。光の屈折により生まれる柔らかな輝きが魅力だ。
若き匠の集団
一般的に職人と聞くと、年配の男性が寡黙に頑なに作っているイメージがあるが、天満切子で働く職人の年齢層は若く、圧倒的に女性が多い。センスがあれば、若くても女性でも門戸は広く、人材募集のリクルートも自社ホームページやSNSで行う。伝統工芸の切子に興味がある人に見てもらいたいからだ。この4月からは新たに芸大出身の女性が入社し頑張っている。
2025年5月号(4/15発行)掲載